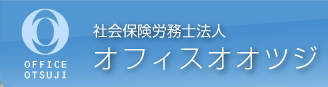2011年7月30日
未払賃銀の確保について
未払い賃金の確保について
最近の労働相談で経営不振のため賃銀が支給されていない。この対策についての相談がありました。
賃確法(賃銀の支払の確保等に関する法律)について
1.制度 法律上の倒産又は中小企業の事実上の倒産の場合に、賃銀を支払ってもらえないまま退職した者を対象に、国が「未払賃銀の立替払制度」を実施する。
2.立替払を受けられる条件
?勤め先が1年以上事業活動を行なっていたこと。
?�勤め先が倒産したこと。(下記??のいづれかに当てはまる場合)
1) 法律上の倒産(破産、特別清算、会社整理、民事再生又は会社再生の手続きに入った場合)
この場合,管財人等に倒産の事実を証明してもらう必要がある。
2) 事実上の倒産(中小企業について、労働基準監督署長が倒産していると認定した場合 ) 労働基準監督署に認定の申請をする
?労働者がその勤め先を既に退職していること。
退職日や申請日等について時間的な条件がある。
3.立替払の対象となる未払賃銀は、定期的な賃銀及び退職金に限る。
4.立替払される額 未払賃銀の額の8割。ただし、退職時の年齢に応じ88〜296万円の範囲で上限がある。
5.手続き
?倒産についての管財人等の証明又は労働基準監督署長の認定
?未払賃金額についての管財人等の証明又は労働基準監督署長の確認
?独立行政法人労働者健康福祉機構への立替払の請求
詳細は労働基準監督署または労働者健康福祉機構に相談のこと。
相談に必要な書類
月々の給与明細書
労働契約書
雇入れ時に、使用者から労働者に労働条件を示した書類
就業規則、賃金規程、退職金規程当の社内規程類
出退勤の記録
以上
投稿者 otuji : 2011年7月30日
| トラックバック (0)
2011年7月28日
法定帳簿の整備要件
賃金台帳の整備保存について
顧問先某社から賃金台帳の保存について質問がありました。
「労働基準法第108条にて各事業所毎に調整し3年間の保存が規定されている。本社で調整し保存することは違反か」が質問の趣旨
労働基準監督署でチェックする法定3帳簿、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿は3年間の保存が義務付けられている。
労働者名簿、入退社関連書類は、労働者の退社日、賃金台帳は、最後の記入月日を起算日とする3年間
賃金債権は2年間で時効消滅、退職金債権は5年で時効消滅
雇用保険被保険者の資格得喪手続き書類は労働者退職後4年間の保存(施行規則第413条)が義務付けられています。後のちのトラブル回避のため7年間保存が望ましい(離職後7年間経過すると職安での被保険者記録も抹消されます。)
賃金計算を本社一括でコンピュウーターを使用して行い、磁気ディスク等の記憶装置に賃銀台帳を保存している場合の要件
? 法定必要記載要件を具備し、かつ、各事業所ごとにそれぞれリーダープリンタを備えている。
? 労働基準監督官の臨検時等賃金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合、直ちに必要事項が明らかにされ、、かつ、写しを提供できるシステムとなっていること(昭和50.10.3基収652、平成7.3.10基収94) (第一法規 ケーススタデイロ道基準法より)
投稿者 otuji : 2011年7月28日
| トラックバック (0)
2011年7月 1日
雇用保険の基本手当日額が引き上げられます
雇用保険の基本手当日額が引き上げられます
厚生労働省は8月1日から5年ぶりに引き上げます
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。
「基本手当日額」は、離職前の賃金をもとに算出した1日あたりの支給額をいい、給付日数は、解雇理由や年齢などに応じ決められます。
今回の引き上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引き上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額が平成21年度と比べて約3%上昇したことによります。
| 現 行 変 更 後 | |
最高額 | 受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとり。 ? 60歳以上65歳未満 6,543円 6,777円 ? 45歳以上60歳未満 7,505円 7,890円 ? 30歳以上45歳未満 6,825円 7,170円 ? 30歳未満 6,145円 6,455円 | |
| |
最低額 | 1,600円 1,864円 | |
基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で低減する率を乗ずる賃金日額の範囲は別に定めるものとする。
投稿者 otuji : 2011年7月 1日
| トラックバック (0)