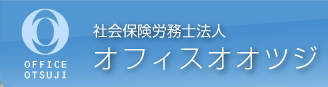2007年10月31日
平成20年度雇用保険料率
平成20年度の雇用保険料率は本年平成19年度と同様の料率に決まりました。
労働保険の徴収法で定められる雇用保険料率は
事業主負担 労働者負担 計
失業等給付のための保険料率 0.8% 0.8% 1.6%
雇用安定事業等のための保険料率 0.35% なし 0.35%
計 1.15% 0.8% 1.95%
平成20年度の雇用保険率
事業主負担 労働者負担 計
失業等給付のための保険料率 0.6% 0.6% 1.2%
雇用安定事業等のための保険料率 0.3% なし 0.3%
計 0.9% 0.6% 1.5%
料率決定の要因
続きを読む
投稿者 otuji : 2007年10月31日
| トラックバック (0)
2007年10月21日
パートタイム労働者の均衡のとれた待遇の確保
パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定しなければなりません。
改正法ではパートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働きの違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じるように規定されました。厚生労働省のパンフレットより紹介します。
続きを読む
投稿者 otuji : 2007年10月21日
| トラックバック (0)
2007年10月11日
改正雇用保険法で施行された募集・採用時の年齢制限の禁止
募集・採用時の年齢制限禁止
平成19年10月1日より、改正雇用対策法が施行され募集採用に年齢制限を設けることが出来なくなりました。
ただし、例外事由として、雇用対策法施行規則第1条の3第1項に該当する6項目は除外されます。
改正雇用対策法第10条
「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
採用に当たっての留意点
募集採用に年齢の制限がないため、職務に適合する者であるか否かの判断を応募者ができるように、必要とする労働者の適正、能力、経験、技能の程度等求められる事項をできるだけ詳細に明示する必要があります。
法令に違反したとき
上記法第10条に違反したとき、ハローワークは、助言、指導、勧告等をし、求人の受理を拒否する事があります。
例外的に年齢制限を行うことが認められる場合 施行規則第1条の3第1項
1号 定年年齢を上限として当該上限年齢未満の労働者を期限の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合
2号 労働基準法等法の規定により年齢制限設けられている場合令
3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合
長期勤続によるキャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合には、上限年齢を定める事が認められます。ただし、
「対象者の就業経験について不問とすること」
「新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等処遇であること」 の2点を満たす必要があります。
3号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種の特定の年齢層において労働者数が相当程度少ない場合に、この特定の年齢層に限定して募集・採用することが認められます。(ただし、期間の定めない労働契約の対象として募集・採用する場合に限ります。)
特定の職種
技法・ノウハウの継承が必要となる具体的な職種を記載 (厚生労働省の定める「職業分類」の小分類または細分類まで。
特定の年齢層
30歳†49歳のうち特定の5†10歳幅の年齢層となります
相当程度少ない
判断する単位は支店や部署単位でなく、企業単位となります。(ただし、雇用管理、人事採用権がある場合は、一部の事業所を単位として判断することも認められます。)
同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者が1/2以下である場合が該当します。
3号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要芸請がある場合
術作品のモデルや、演芸等の役者の募集・採用において、表現の真実性等のために、特定の年齢層の労働者に限定して採用・募集することが認められます。
3号のニ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対照となる者に限定して募集・採用する場合
60歳以上の高年齢者に限定して募集・採用する場合に、年齢制限をすることが認められます。また、特定の年齢層の雇用を促進する国の施策(雇入れ助成金等)を活用するため、その施策の対象となる特定の年齢層に限定して募集・採用する場合には、年齢制限をすることがみとめられます。
投稿者 otuji : 2007年10月11日
| トラックバック (0)
2007年10月 5日
短時間労働者に対する差別的取扱いに禁止
パート労働法では短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止(第8条)が定められています。
特に賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用に対する待遇が上げられています。前回、福利厚生施設の利用を解説しましたが、今回賃金の決定について解説したいと思います。
4.差別的取扱いの禁止 法第8条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別取扱の禁止)
通常の労働者と同視すべき短時間労働者とは1).業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という)が当該事業に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(職務内容同一短時間労働者)であって、2).当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結している者のうち、
3).当該事業所における慣行その他の事情から、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間
4).職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれる者
短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的取扱いをしてはならない。
5.賃金通常の労働者と同一の方法による賃金の決定法第8条及び第9条で定めるもののほか、職務の内容に関連して支払われるもの以外の手当についてもその就業の実態、通常の労働者との均衡を考慮して定めるよう努めること。
職務の内容に密接に関連して支払われる以外の手当については下記のとおり定められました。
† 通勤手当
† 退職手当
† 家族手当
† 住宅手当
† 別居手当
† 子女教育手当
† †††までに掲げるもののほか、名称の如何を問わず支払割れる賃金の内職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金
投稿者 otuji : 2007年10月 5日
| トラックバック (0)
2007年10月 3日
パートタイマーに対する福利厚生
改正パートタイマー労働法では、通常の労働者に対して利用させる福利厚生施設をパートタイマーにも利用の機会を与え差別をしてはならないと定められました。
その福利厚生施設とは下記の施設とされました
4.「福利厚生」現行の指針は、施設の利用に限定されているが、パートタイマーの実態はさまざまであり画一的に実施することは馴染まない。そのため、指針上では、短時間労働者の就業の実態、通常の労働者との均衡を考慮した取扱をするように努めるものとする。厚生労働省令で定める福利厚生施設は下記のとおり定められました。
† 給食施設。
† 休憩室。
† 更衣室
続きを読む
投稿者 otuji : 2007年10月 3日
| トラックバック (0)
2007年10月 2日
パートタイマーの労務管理
平成20年4月から施行される改正パート労働法については、企業が今まで認識していたパートタイマーの労務管理の概念を一掃しなければならないことです。今後この解説を記述したいと思います。
「パートタイム労働指針」について
事業者が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善に関する基本的考え方
1.労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、均等法、育児・介護休業法、雇用保険法等労働者保護法令は、短時間労働者についても適用がある。
2.短時間労働者の雇用管理については、多様な就業実態を前提としてその職務の内容、職務の成果、意欲、能力、及び経験に応じた待遇をするように努力すること。
(この点は昨日の雇用対策法の趣旨に〓がります)
3.雇用改善の措置を講ずるに当たり、その雇用する通常の労働者その他の労働者の労働条件を合理的理由なく一方的に不利益に変更する事は法的に許されない。
所定労働時間が通常の労働者と同一の有期雇用労働者は短時間労働者とはならない。通常の労働者と見る。
(上記のことは有期雇用労働者であるからとして通常の労働者との雇用条件に差別をつけることは出来ません)
以下順を追って解説をブログに掲載します
続きを読む
投稿者 otuji : 2007年10月 2日
| トラックバック (0)